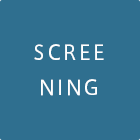
25卒 2次面接
総合職(営業職)
- Q. 企業研究で行ったことを教えて下さい。
- A.

萩原電気ホールディングス株式会社
萩原電気ホールディングス株式会社の本選考のフローや志望動機、グループディスカッションの内容や内定者のアドバイス、入社を決めた理由の一部を公開しています。ぜひ、詳細ページにて全文を確認し、選考対策に役立ててください。
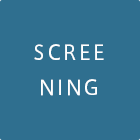
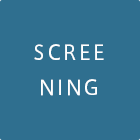
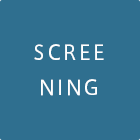











| 会社名 | 萩原電気ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ハギワラデンキホールディングス |
| 設立日 | 1958年12月 |
| 資本金 | 60億9900万円 |
| 従業員数 | 854人 |
| 売上高 | 2587億4200万円 |
| 決算月 | 3月 |
| 代表者 | 木村 守孝 |
| 本社所在地 | 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2丁目2番1号 |
| 平均年齢 | 42.3歳 |
| 平均給与 | 712万円 |
| 電話番号 | 052-931-3511 |
| URL | https://www.hagiwara.co.jp/ |
就活会議を運営する就活会議株式会社は、届出電気通信事業者として総務省の認可(許可番号 :A-02-18293)を受けた会社です。